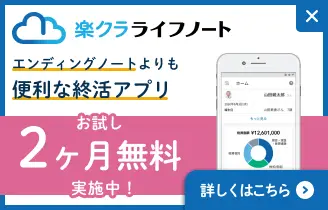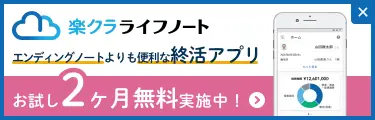【2022年3月】2022年4月から成人年齢が18歳に 相続税・贈与税への影響は?
終活とは?準備でやるべきこと6つ|始める時期・注意点も解説
- 公開日:
- 更新日:

この記事の内容
この記事をおすすめする人 終活をいつ・どのようにはじめたらいいかわからない方 この記事のポイント
おすすめの資産管理・終活アプリは『楽クラライフノート』 |
少子高齢化や価値観の多様化が進むなかで、充実したシニアライフや自分らしい人生の最期について考え行動する、「終活」を始める人が増えています。そのようなトレンドがある一方で、「終活」という漠然とした言葉に、何をすればよいのか戸惑う方も多くいるのではないでしょうか。
こちらの記事では、終活の定義やメリットといった基本的なことから、始める時期や進めるなかで注意すべき点まで、くわしく解説します。
終活とは

終活とは、もっているモノや資産のほかに、情報や気持ちの整理をおこない、今後の人生と自分の死後を考えた準備をすること。相続について遺言書を書くことはよく知られていますが、これに限らず、さまざまなことがらを生きているうちに整理していきます。
具体的には、以下のような例が挙げられるでしょう。
- もっている資産を整理し、今後の管理の仕方や相続について考える
- 人生をふりかえって自分史を書く
- どのようなお葬式にしたいか考えて、家族に共有する
モノや思い出を整理することは、自分自身の人生をふりかえることです。自分の歴史をたどりながら、人生の最後に向けて「自分はどのようにありたいのか」をあらためて考えることで、シニアライフの人生設計がより具体的になっていきます。
またわたしたちは日々インターネット上にさまざまなデータを保管したり、メールやSNSで情報を発信したりしています。そうしたネット上のデータも個人の大切な財産であり、それらを整理して死後どのように扱うかを決める、「デジタル終活」に取り組む人も増えています。

終活が広まった背景
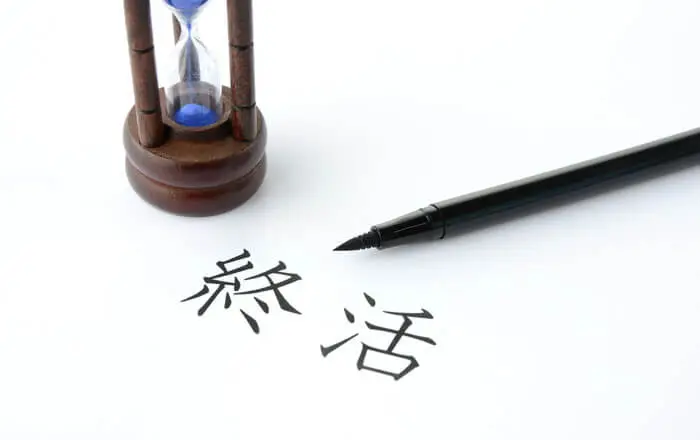
終活という考え方が生まれたことには、日本が直面している少子高齢化と平均寿命の伸びが大きく影響しています。
厚生労働省が作成する平均寿命の年次推移によると、平成2年にはそれぞれ、75.92歳(男性)81.90歳(女性)だった平均寿命が、平成30年になると81.25歳(男性)、87.32歳(女性)に。わずか1世代で平均寿命が約5歳も伸びています。
(参照:厚生労働省「平成30年簡易生命表の概況」2018年)
一方で、親世代を支える子世代の人口は減るばかりです。
歳を重ねるなかで人々が自分の死後にのこされる家族の負担を考えるようになったり、長いシニアライフの充実を意識したりすることを背景に、終活は広まってきました。
終活をおこなう3つのメリット

自分の人生をふりかえり今後を考える「終活」。ここでは、終活に取り組むメリットを3つご紹介します。
1. 家族の負担を減らせる
終活をおこなうメリットのなかでも、家族の負担が減らせることはとくに大きなポイント。実際に、終活をする(したい)理由として、7割以上の人が「家族に迷惑をかけたくないから」という理由を挙げています。
(参照:楽天インサイト株式会社「終活に関する調査」2019年)
遺品整理が楽になり、精神的な負担がやわらぐ
家族にとって、大切な人の死後にのこされたモノは思い出深く、簡単には処分できません。整理するには、時間や労力だけでなく気持ちへの大きな負担もかかります。
いらないモノは自分で処分したり人に譲ったりして整理し、のこしておきたい思い出の品は前もって家族に共有しておきましょう。
老後や死後の資金管理、運用が楽になる
家族であっても、亡くなった人の銀行からお金を引き出すためには、書類の準備と手続きにたくさんの時間と手間がかかります。また最近はネット上でも資産運用ができるようになるなど、さまざまな場所に資産が散らばっているケースも多く、さらに負担がかかることも。
終活をとおして資産を整理し、家族に情報ややるべきことをきちんと伝えていれば、互いの負担を減らしスムーズに引き継げます。
2. シニアライフを充実させられる
「老後資金2000万円問題」などを受け、将来に漠然とした不安をもたれている方も多いのではないでしょうか。そうした不安をやわらげ、いまの生活をより楽しむためには、もっている資産とこれから必要になるお金を知ること。
退職を機に資産の運用に挑戦したい方も、まずは分散されている資産の全体を把握することから始めてみましょう。そのうえで、介護やお葬式に必要なお金を洗い出し、自分のために使えるお金を明確にしてから今後どのように使っていきたいか道筋をたてることが大切です。
3. 死後の不安を取り除ける
相続やお葬式についての本人の意思がのこされていないと、大切な人を亡くした悲しみのなかで、いちから家族が話しあいをしなければなりません。本人の意思がわからないまま決断するのは難しくトラブルになりやすいほか、家族の心の負担も大きくなります。生前から自分の死後のことを考えて家族に意思を伝えておくと、自分の意思が反映でき家族も救われるはずです。
また最近は平均寿命が伸びたことにより、生前であっても子どもが高齢に達していることがあります。早めに終活に取りかかり、身のまわりのモノの生前整理など体力を使う作業を終わらせておくことで、子どもに負担をかける心配もなくなります。
終活を始めるタイミング

終活を始めるタイミングは、65歳以降が多くなっています。(出典:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部「シニアの終活・資産管理に関する親子比較調査(2022年11月)」)
60代は、退職後でまとまった時間がとりやすく、自分の子どもも家庭を築きはじめる年代。どのようなシニアライフにしたいかが明確になり、終活を始めるのに適した年齢であるのもうなずけます。
しかし、終活を始めるタイミングは人それぞれ。自分の体力を考えて、早めに始めるという選択肢もあります。家族と相談しながら、自身のライフプランに沿ったタイミングで始めてみましょう。
終活準備でやるべきこと6つ

ここからは、より充実したシニアライフを満喫し、自分らしい最期を迎えるための準備として、やるべきこと6つをご紹介します。
1. もっている財産を洗い出す
まずは持っている資産をきちんと整理することから始めましょう。子世代が、終活で親世代にやってもらいたいことのうち、「口座や金融資産の管理」が回答者全体の45.1%と、全体で2番目に高い割合となっています。(出典:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部「シニアの終活・資産管理に関する親子比較調査(2022年11月)」)財産の洗い出しでは、金融機関・支店名、金融商品の種類、預金の種類などを書き出していきます。家族が相続で必要な手続きをおこないやすいように、口座番号などくわしい情報までのこしておきましょう。
そのあと、用途が同じになっている銀行口座が複数あれば解約するなどの資産の整理をしておくと、相続手続きが簡単になり、家族の負担を軽減できます。
2. 身の回りのものの整理をする
のこしておきたいものを先に考え、それ以外のものは処分していきましょう。実は、子世代が、終活で親世代に最もやってもらいたいことは「持ち物の整理」で、回答者の47.1%が「やってほしい」と回答しています(出典:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部「シニアの終活・資産管理に関する親子比較調査(2022年11月)」)。いらないものはゴミに出すのもいいですが、思い入れのあるものはリサイクルしたり人に譲ったりもできます。いまのこっているものは、今後どのように処分してほしいのかを家族に伝えておくと、遺品整理の負担が軽くなります。
3. エンディングノートや終活アプリに記録する
家族に共有しておくべきことや自分の希望をのこすために、エンディングノートや終活アプリに記録していきましょう。ぜひ以下の項目を参考にしてみてください。
- 略歴や個人情報(出身地、経歴、生年月日、趣味や特技など)
- 治療や介護の希望
- お葬式やお墓の希望
- 資産情報
- 遺言書の有無や保管場所
- かかりつけ医やソーシャルワーカーの情報
- ペットの情報(かかりつけ医、トリマー店など)
- 家族へのメッセージなど
身のまわりのものごとを整理したうえで意思表示をするという意味合いが大きいですが、終活を始めたばかりで何をしたらいいかわからないときに、情報や気持ちを整理したり、今後すべきことを明確にしたりするのにも役立ちます。まずは気楽に書きはじめてみましょう。
4. 遺言書をつくる
エンディングノートや終活アプリで自分の状況と気持ちを整理したら、続いて法的拘束力のある書類をのこす準備をしましょう。遺言書をつくることで、財産の配分を決められたり相続財産の処分ができたり、法定相続人ではないお世話になった人や団体にも相続できるようになったりと、自分の意思を反映しやすくなります。
5. かかりつけの病院で終末期医療などに関する希望を出す
自分らしい最期を迎えるために、どのようなケアを望んでいるのか、自分の希望を医師や家族に伝えておくことが大切です。
とくに自分の意思表示が大切なのが「延命治療と終末期医療、どちらを受けたいか」。本人の判断能力がなくなり、延命治療を受けるか終末期治療を受けるかの判断を家族がくだすことになると、とても大きな気持ちの負担をかけてしまいます。自分で判断できるときに意思決定し、治療に対する自分の気持ちを家族に共有しておきましょう。
6. お葬式やお墓の準備をすすめる
喪主はだれにするのか、どのくらいの規模のお葬式がいいのか、どのようなスタイルのお葬式やお墓にするのか、など自分の希望を洗い出していきます。お葬式やお墓は生前契約を結ぶことができます。複数の葬儀社に相談して見積もりをとり、よく考えてから決断しましょう。
お葬式・お墓は、大切な家族やお世話になった人との最後の接点となります。自分の希望を反映するためにしっかり生前準備をおこないましょう。

終活で気をつけること

自分と家族にとってたくさんのメリットがある終活。取り組むなかで注意すべきポイントを3つご紹介します。
1. 家族と話しあおう
子どもは、親の将来についてたくさんの心配ごとを抱えています。
「親の資産がどのくらいあり、それで老後資金がまかなえるのか」「足りない場合、どのくらい自分が用意しないといけないのか」などと不安に思ったり、いざというときにお葬式やお墓をどうしたらいいかわからなくても「死後」の話題に触れづらかったり……。
終活を進めていることを伝えるだけでも、家族の心配ごとを減らせます。相談の意味あいだけでなく家族の不安をやわらげるためにも、終活を始める際には家族と対話ができるとよいでしょう。
またせっかく終活をしてお葬式やお墓などのプランを立てても、実行されなければ意味がありません。思い描いた最期を迎えられるよう、家族にきちんと希望を伝えることが大切です。思いを形にしてのこす方法として、エンディングノートや終活アプリを利用する人が増えています。

2. 詐欺に気をつけよう
老後の生活やお金、お葬式やお墓などへの不安から取り組む人が多い終活。メリットもたくさんある反面、そうした不安を逆手にとった詐欺の被害が後をたたないのも事実です。
たとえば、本人が生前に契約していた葬儀社から、後になって家族に予定外の高額な費用が請求されたり、「終活セミナー」をうたうイベントで高額な商品を契約させられたり……。巧妙な手口が増えているため、「話がよすぎるな」と思ったらまずは家族や知人に相談して、終活は焦らず慎重に進めましょう。
3. 遺産相続のトラブルを未然に防ごう
遺産相続について取り決めをおこなうときには、兄弟姉妹で不公平にならないよう気を付けましょう。遺産相続でトラブルが起きるケースの大半は「兄弟姉妹の不平等感」で、資産の大小に関わらずトラブルが起こり得ます。
遺言書を作成したり、相続人の範囲を確定したりするなど、終活を行うときに遺産相続のトラブルを未然に防止するよう努めましょう。生前から親族間でコミュニケーションを取り、相続人全員が納得するよう話し合いを重ねておくことも重要です。
4.ペットの将来も考えておこう
ペットを飼っている人は、ペットの引き渡し先やお世話をお願いできる人を決めておく必要があります。相続人がいる場合は相続人がペットを相続することになりますが、相続人がいない場合は、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」などの事務手続きが必要です。
負担付遺贈や負担付死因贈与とは、財産をあげる代わりにペットの飼育をお願いするということです。おひとりさまで相続人がいない人は、生前にペットの飼育をお願いできる人を探しておくようにしましょう。
5. 困ったらプロに頼ろう
いまや一般的になった「終活」ですが、ひとりで進めるのは骨の折れる作業です。終活についての不安のなかでも、そもそも「何から手をつけたらよいかわからない」という思いを抱える人がもっとも多くなっています。
(参照:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部「シニアの終活・資産管理に関する親子比較調査(2022年11月)」)
悩んでしまったら、ひとりで抱え込まずに家族など周りの人を頼るほか、専門家からアドバイスをもらうのもひとつの選択肢です。
とくに相続については、法律や契約などの専門知識が求められます。間違った対応をしてしまうと遺書が無効になったり、相続税などで損をしたりすることもあるので、慎重に進めることが大切です。
おすすめの終活アプリは「楽クラライフノート」
終活アプリ「楽クラライフノート」は、これから終活を始めようとしている方にピッタリのアプリです。エンディングノートとして相続に関する意向や、自分自身の健康・介護に関する希望、お葬式やお墓に関する希望などを登録できます。また、生前のうちから資産管理や家計管理ができることも特徴の一つで、老後に必要な資金をシミュレーションできる機能も搭載されています。
なお、楽クラライフノートに記録した情報は、アプリを通じて家族とも共有が可能。たとえば、預金口座と残高の情報を共有したり、不動産や証券も含めたすべての資産情報を共有したりといったことも可能です。
登録した情報はスマートフォン本体ではなくインターネット上に保存されるため、ID・パスワードさえ覚えておけば機種変更時も特別な操作は必要ないので安心してご利用いただけます。
まとめ
終活は、モノや資産のほかに情報や気持ちの整理をおこない、今後の人生と自分の死後を考えた準備をすること。家族の負担や自分の不安をやわらげるメリットがある一方で、やることが多く、自分だけで進めるのが難しいのも事実です。
家族で話しあいながら進めることで、やらなければいけないことや不安も共有できます。楽クラライフノートを活用して、家族と共に終活を進めていきましょう。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)
資産管理やエンディングノートの登録、家族へ情報共有したい方には、終活アプリ『楽クラライフノート』がおすすめ。自身の現状や思い、資産・家計をアプリで一元管理でき、老後に向けた健康やお金などにまつわる不安を解消します。また登録した情報は、伝えたい家族に絞って共有可能。これからの人生を、よりよく生きるための取り組みをサポートします。
『楽クラライフノート』をご利用いただいている方に、おすすめ情報をお届け。自身の現状や思いを登録したり資産・家計管理をしたりするなかで、「専門知識を持ったプロの方に相談してみたい」など自分の終活がうまくできているのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。『楽クラライフノート お金と終活の情報サイト』から、アプリ会員様限定で専門家への無料相談の申し込みが可能です。
また、お得な優待も揃えておりますのでぜひご活用ください。
『楽クラライフノート』をご利用いただいている方に、おすすめ情報をお届け。自身の現状や思いを登録したり資産・家計管理をしたりするなかで、「専門知識を持ったプロの方に相談してみたい」など自分の終活がうまくできているのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。『楽クラライフノート お金と終活の情報サイト』から、アプリ会員様限定で専門家への無料相談の申し込みが可能です。
また、お得な優待も揃えておりますのでぜひご活用ください。