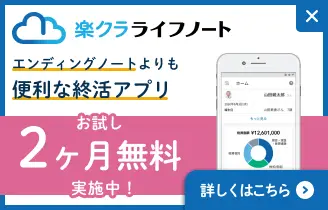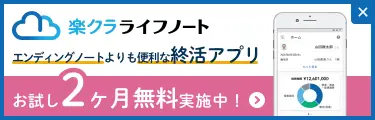お彼岸にやってはいけないことはない|世間でいわれる「タブー」と誤解
香典の相場はいくら?関係別の目安金額や渡す際のマナーを解説
- 公開日:
- 更新日:

この記事の内容
株式会社セレモアは首都圏全域で事業展開を行っており、約2,500団体の官公庁、企業と福利厚生の契約をさせていただいております。
NTTグループへお勤めの方とそのご家族の皆様にはお花・介護用品・患者移送・お仏壇・お葬儀のことまで各種サービスを経済的にご利用いただくことが出来ます。
この記事をおすすめする人 近親者のお葬式への参列を控えている方 この記事のポイント
「自分が生きた証や人生を振り返っておきたい」と考えている方には、終活アプリ『楽クラライフノート』がおすすめ。 |
お通夜、お葬式の際には、基本的に香典を持参します。香典はお通夜やお葬式の際に、お悔やみの気持ちを込めてお供えする金品のことです。しかしお通夜やお葬式に行く機会はそう頻繁にあるわけではありません。そのため香典のマナーについて知る機会がないという人もいるのではないでしょうか。
この記事では「あまりお通夜やお葬式に行ったことがない」という方に向けて、香典の相場や渡し方、香典袋の書き方など、香典にまつわるマナーについて詳しく解説します。
親族への香典の相場

親族が亡くなったとき、どれほどの金額を香典として包めばよいかは、亡くなった人との関係と自分の年齢によって変わってきます。以下の表の、「両親」「祖父母」などと書いてあるのは自分と亡くなった人との関係、「20代」「30代」とあるのは自分の年齢です。ぜひ参考にしてください。
20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |
両親 | 3万円〜10万円 | 5万円〜10万円 | 5万円〜10万円 | 10万円 |
祖父母 | 1万円 | 1万円〜3万円 | 3万円〜5万円 | 5万円 |
兄弟 | 3万円〜5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
おじ・おば | 1万円 | 1万円〜3万円 | 3万円以上 | 3万円以上 |
そのほかの親戚 | 5000円〜1万円 | 5000円〜1万円 | 5000円〜1万円 | 5000円〜1万円 |
近親者のお葬式には香典を出さない場合もある
一方で、近年では近親者のお葬式に香典を出さないケースも見られるようになっています。鎌倉新書がおこなった「第4回お葬式に関する全国調査」によると、親、祖父母、兄弟姉妹のお葬式の場合、4割以上の人が香典を出さなかったと回答しています。また、これが自分の親のお葬式ともなると、香典を出さなかった人は61.4%にも上ります。
この点から、最近では近親者であると香典を出さないことも多くなっているようです。もっとも、自分の親のお葬式となると喪主を務めるケースが少なくないため、香典という形をとらずに相応の費用負担をするケースもあると考えられます。
とはいえ、お葬式はたとえ家族葬であっても数十万円程度のお金がかかるもの。香典を出さないという選択をとる場合は家族間のトラブルを起こさないためにも、兄弟姉妹といった自分と近しい親族と相談するほうがよいといえます。
勤務先の香典の相場

もし勤務先の従業員などが亡くなった場合、遺族が家族葬を選択した場合は弔問をしないほうが無難です。しかし、一般葬であったり家族葬でも出席が許されたりするときは、香典を持参しましょう。香典の相場は、自分と亡くなった人の関係によっても変わってきます。
上司
上司が亡くなったときの香典は、5000円〜1万円が相場です。香典を贈る側の世代別に、表にしましたのでご覧ください。
香典を贈る人の年齢 | 相場 |
20代 | 5000円程度 |
30代〜40代 | 5000円〜1万円 |
50代〜60代 | 1万円以上 |
お葬式はあってほしくないものですし、香典も弔いの気持ちを形として包むものです。よって、多く包めば遺族に喜ばれるというわけではありません。とくに、自分の年齢、役職、立場から大きく外れるような多額の香典を包むと、香典返しを考えなくてはならないため遺族の負担となったり、地域の風習から外れすぎてしまうことも。そのため相場どおりの金額とするのがよいでしょう。
同僚
同僚が亡くなったときの香典の相場は5000円程度となります。こうしたケースでは、部署や同期の連名で香典を出すこともあります。
原則的に、取引先などの不幸で会社として香典を出すときは、個人で香典を出さないのがマナーです。しかし、おなじ会社のとくに親しかった同僚が亡くなった場合は、会社や部署として香典を出していても個人で別に出してもよいでしょう。
部下
部下が亡くなったときの香典は、3000円〜1万円が相場です。
香典を贈る人の年齢 | 相場 |
20代 | 3000円程度 |
30代〜40代 | 5000円〜1万円 |
50代〜60代 | 1万円以上 |
これも繰り返しとなりますが、自分よりうえの立場の人より多くの香典を包んでしまうと、その人の立場をなくしてしまうことになります。やはり、相場を大きく超えるような香典を包むのは避けたほうが無難です。
単独ではなく、連名で香典を出す場合も多い
先ほどもすこし解説しましたが、会社内の人が亡くなったときは部署や有志などの連名で香典を出す場合も少なくありません。こうしたときは、まず社内で話しあい、足並みを揃えて香典を出すようにしましょう。
取引先関係への香典
取引先の関係者が亡くなったときの香典の相場は1万円以上となり、金額は香典をだれの名前で出すかによって変わってきます。まずは下の表をご覧ください。
香典を贈る人の役職 | 相場 |
社長 | 3万円〜10万円 |
役員(社長以外の代表取締役、取締役、執行役員など) | 1万円〜10万円 |
担当者 | 1万円〜3万円 |
取引先など、仕事上でのつきあいがあった人の不幸の際もおなじで、会社の一員としての対応が求められます。
訃報を受けたらまず上司に相談しましょう。会社で香典の金額などを規定している場合もありますし、上司が具体的な対応を決める場合もあります。通夜・お葬式への参列や弔電、供花の手配なども可能な限り早くおこなうことが大切です。
香典は交際費として経費で落とせる
会社としての支出が必要となる香典は、経費として計上できます。贈る先によって勘定科目が異なり、取引先の場合は「接待交際費」、従業員関係の場合は「福利厚生費」という仕訳になります。
ただ、相場より多くの金額を包むと、税務調査の際に経費として認められない可能性があります。この点は、注意してくださいね。
友人関係への香典

ここでは、友人本人が亡くなった場合、友人の親が亡くなった場合に分けて解説します。総じて見ると、1万円以内が相場です。
友人
つきあいがある友人が亡くなったとき、その関係性と自分の年齢によって、香典として包む金額が変わってきます。
まず、親しい友人が亡くなった場合を見てみましょう。
香典を贈る人の年齢 | 相場 |
20代 | 3000円〜1万円 |
30代〜50代 | 5000円〜1万円 |
60代以上 | 1万円程度 |
続いて、亡くなった人とおたがいに知りあっているような関係や近所の人のお葬式での香典相場です。
香典を贈る人の年齢 | 相場 |
20代 | 3000円〜5000円 |
30代〜50代 | 3000円〜1万円 |
60代以上 | 5000円〜1万円程度 |
友人の親
友人の親が亡くなったときの香典は、3000円〜5000円程度となります。
ただ、もし自分の親が亡くなっていて香典をいただいていた場合は、そのときとおなじ金額を包むとよいでしょう。また、友人とは親しくても親御さんとは面識がない場合もありますが、そうであっても葬儀に参列し香典を包んで弔慰を示すのはまったく問題がありません。
どんな相手にも絶対にやってはいけないこと

香典には、包む「金額」や「包み方」にもマナーがあります。以下で説明するのは親族や会社関係といった相手を問わず、やってはいけない大原則となります。
4や9など不吉な数字や偶数は避ける
まず、4(死を連想)や9(苦を連想)といった不吉な数字となる金額を包んではいけません。つまり、4万円や9万円はNGということです。次に、偶数、つまり2万円や6万円といった金額を包んでもいけません。これは、割り「切れる」のが縁起が悪いとされているためです。
先ほど、香典は多すぎる金額にするとよくないと説明しましたが、反対に少なすぎるのも考えものです。たとえば、上司のあなたが亡くなった部下への香典として1000円しか包まなかったら、「部下を軽んじているのか」との印象を与えてしまうことを想像できるのではないでしょうか。
また、相場から外れないという意味では、地域によって香典の相場が異なるケースもあります。不慣れな土地でのお葬式は、地元の人に香典の相場やそのほかのマナーについて質問するのがよいでしょう。
バラよりまとまったお札を包んだほうがいい
1万円を包む場合、1万円札1枚を包むのであれば問題ありませんが、1000円札を10枚包むのはやめましょう。不幸が「重なる」ことを連想してしまうためです。また、遺族やお葬式の受付の人が、お札を数えるのに手間がかかってしまいます。
10万円を包む場合は、1万円札より大きい金額の紙幣がないため、1万円札10枚を包んでも問題ありません。
通夜・お葬式に参列するときは香典の作法を知ろう

金額や包み方以外にも、香典の作法があります。ここでは作法を簡単に記しますが、別の記事に詳細を掲載してありますので、併せて参考にしてください。
香典を袱紗に包む
香典をカバンなどにそのまま入れてお葬式会場を訪ねるのはマナー違反です。必ず袱紗(ふくさ)に包みましょう。袱紗は、文房具店などで販売されています。
香典袋の書き方
香典袋の書き方は一律に同じというわけではありません。宗教・宗派によって書き方が異なります。また外袋の水引上部の名目や下部の名前、中袋の金額など、袋によっても書き方のポイントがありますので注意しましょう。

香典の渡し方
香典は受付で渡す(正確には「お供えする」)のが一般的です。袱紗の包みを開き、香典袋に書いた文字を受付の人が読める向きにして、渡しましょう。

香典返しの相場
香典を受け取る喪主・遺族の立場としては、香典返しをする必要があります。香典返しで贈る品物はいただいた香典の3分の1〜半分の金額の品物を選ぶのが相場となっています。通夜・お葬式での親族の香典相場は比較的近親の人が亡くなった場合、法事の香典相場は近親者でない人(親戚や友人関係など)を想定した金額です。
お葬式・法事の区別、亡くなった人 | 通夜・お葬式の香典相場 | 法事の香典相場 | ||||
親族 | 勤務先関係 | 取引先関係 | 友人関係 | 一周忌 | 三回忌 | |
金額 | 1万円〜10万円 | 1万円前後 | 1万円〜10万円 | 1万円以内 | 1万円以内 | 3万円以内 |

まとめ
結婚式のようなおめでたい席では、相場より多くのご祝儀を包むケースも見られますが、お葬式は不祝儀ですので多く包めばよいというわけではありません。相場を知り、それに見あった金額を包むのがよいでしょう。それと同時に、説明した不吉な数字となる金額は包まないなどのマナーを守るのも必要です。
また、会社の取引先関係の人が亡くなったとき、どうしても個人として香典を出したい場合は上司などと相談するのがベターです。個人で「勝手なことをした」と思われてしまうこともあり得ますので、気をつけましょう。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)
「葬儀やお墓に関する思いを子どもに伝えたいが、なかなか話せない」という方には、終活アプリ『楽クラライフノート』がおすすめ。葬儀やお墓の種類や費用などの意向をアプリの記入項目に沿って登録し、いつでも書き換え可能。登録した情報は、伝えておきたい家族に共有できます。
『楽クラライフノート』をご利用いただいている方に、おすすめ情報をお届け。自身の現状や思いを登録したり資産・家計管理をしたりするなかで、「専門知識を持ったプロの方に相談してみたい」など自分の終活がうまくできているのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。『楽クラライフノート お金と終活の情報サイト』から、アプリ会員様限定で専門家への無料相談の申し込みが可能です。
また、お得な優待も揃えておりますのでぜひご活用ください。
『楽クラライフノート』をご利用いただいている方に、おすすめ情報をお届け。自身の現状や思いを登録したり資産・家計管理をしたりするなかで、「専門知識を持ったプロの方に相談してみたい」など自分の終活がうまくできているのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。『楽クラライフノート お金と終活の情報サイト』から、アプリ会員様限定で専門家への無料相談の申し込みが可能です。
また、お得な優待も揃えておりますのでぜひご活用ください。